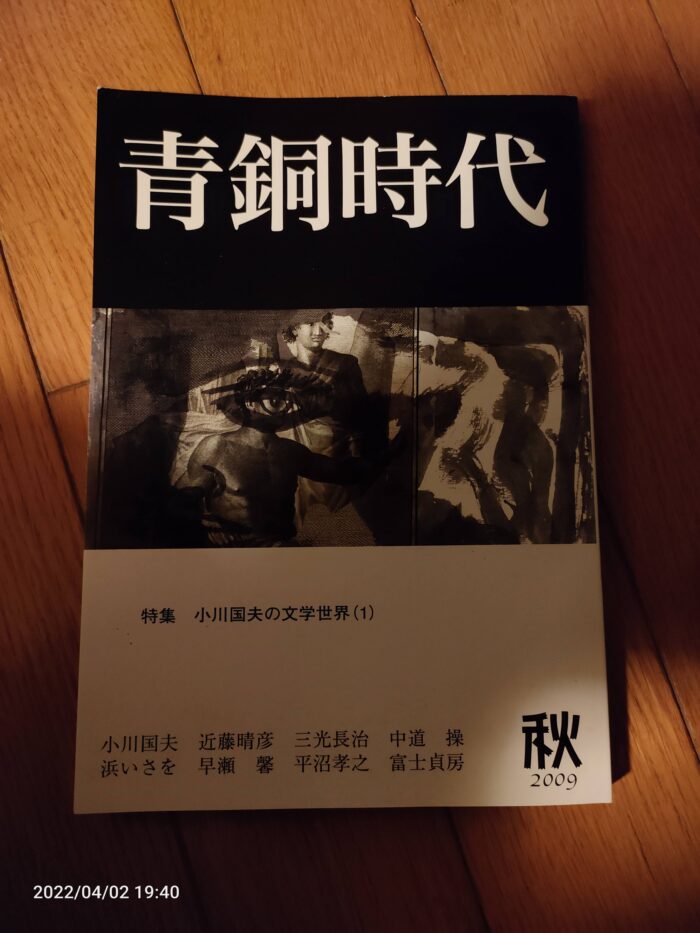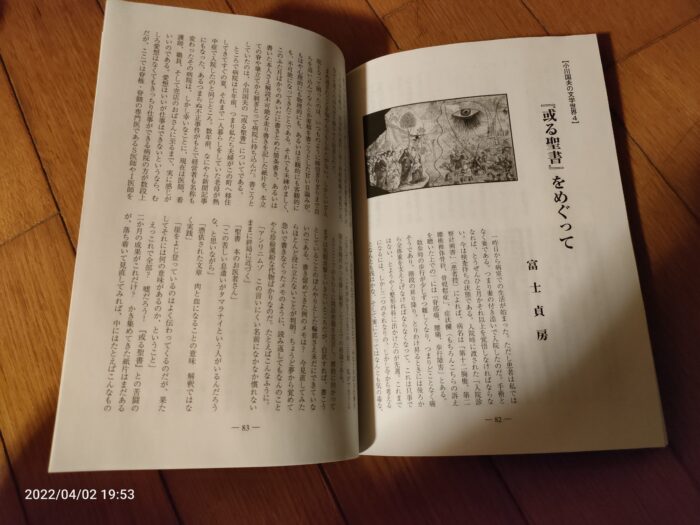『或る聖書』をめぐって
富士貞房
一昨日から病室での生活が始まった。ただし患者は私ではなく妻である。つまり妻の付き添いで入院したのだ。手術となれば、とうぜんひと月かそれ以上を覚悟しなければならない。今は検査待ちの状態である。入院時に渡された「入院診察計画書」(患者控)によれば、病名は「第十二胸椎、第二腰椎椎体骨折、骨粗鬆症」、症状欄(もちろんこちらの訴えを聴いた上での)には「脊部痛、腰痛、歩行障害」とある。
散歩時の歩行が少しずつ難しくなり、つまりどことなく痛そうであり、階段の昇り降り、とりわけ昇るときには後ろから全体重を支え上げなければならなくなって、これは只事ではない、とようやく整形外科に出かけたのが先週。これまでになるには、しかし二つのそれなりの、しかし今から考えるとなんとも浅はかな、そして妻にとってはなんとも気の毒な、理由があった。すなわち本人が不具合やら痛みをうまく言葉にできなかったこと、そしてこちらの方が主要な理由だが、この歩行困難は、認知症の進行に伴う神経組織の劣化では、などと素人の浅知恵を働かせた結果なのだ。
まあ過ぎたことを悔やんでもしかたがない。しかしいざ入院となって困ったのは、いつものように締切ぎりぎりまで自らを追い込んでなんとか原稿を書こうとした甘い目論みが、もはや心理的にも物理的にも、あるいは主観的にも客観的にも、不可能になってきたことである。それでも未練がましく、このふた月ばかりのあいだに書きとめた箇条書き、あるいは書いた本人さえ解読不可能な走り書きを記した紙片を、本立ての脊や筆立てから剝ぎとって病院に持ち込んだ。書こうとしていたのは、小川国夫の『或る聖書』についてである。
ところで病院は七年前、つまり私たち夫婦がこの町へ移住してきてすぐの夏、それまで一人暮らしをしていた老母が熱中症で入院したのと同じところ。数年前、なにやら新聞記事にもなった、あるつまらぬ不正事件がもとで経営者も名称も変わったその病院は、しかし幸いなことに、現在は医師、看護師、職員、そして売店のおばさんに至るまで、実に感じがいいのである。愛想はいいが仕事はできないというなら、むしろ愛想はなくてもきっちり仕事ができる病院の方が数段上だが、ここでは脊椎・脊髄の専門医であるS医師やI医師をはじめ、お掃除のおばさんに至るまで、みなてきぱき仕事をこなしている。これが少なくともこの三日間、私ができうる限り客観的かつ冷静に観察したうえでの結論である。
さてここでおもむろに閑話休題を宣言し、標的に向かってまずは先制攻撃といきたいところだが、白状すれば、書こうとしていることのぼんやりとした輪郭さえ未だにできていないのである。書き留めてきた例のメモは? 今見直してみたらほとんど役に立たないことが判明。ちょうど夢から覚めて急いで書きなぐったメモのように、読み返してもなんのことやら珍紛漢紛な代物ばかりなのだ。たとえばこんなふうに。
「アシリニムゾ この言いにくい名前になかなか慣れないままに終局に近づく」
「聖書 本のお医者さん」
「この苦しい息遣いがタマラナイという人がいるんだろうな、と思いながら」
「憑依された文章 肉と血になることの意味 解釈ではなく実践」
「崖をよじ登っているのはよく伝わってくるのだが、果たしてそれに何の意味があるのか、ということ」
えっこれで全部? 嘘だろう! 『或る聖書』との苦闘の二か月の成果がこれだけ? かき集めてきた紙片はまだあるが、落ち着いて見直してみれば、中にはたとえばこんなものまで含まれていた。
「歯の間にはさまったものをせせり出す時のような音」
これは結局は途中で放棄した中国語の発音についてのメモらしい。
やはりあきらめるしかないか。もちろん『或る聖書』が収録された『新潮現代文学65 小川国夫』は、妻の着替えなど急いで詰めた紙袋の底に持って来てはいる。読み直そうか。いや天国の小川氏には悪いが、少なくともいま、もう一度読み返すだけの精神的エネルギーはない。そしていま思い出したのだが、二か月前に読みだして間もなくにも、やはり同じような「荷の重さ」を感じたのではなかったか。小川国夫作品がこれほどまでに読みにくいものだとは、実は今回はじめて実感した。そういえば、先ほどのメモのいくつかはすでにその事実を暗示している。
多分にそれは最近の私自身の精神状態が深く影響してのことであるに違いない。要するに小川作品に限らず、また文学作品に限らず、とりあえず自分にとっての必要性という濾過装置にひっかからないものには一向に食指が動かなくなってきたのだ。いま「自分にとっての必要性という濾過装置」などと意味不明の言葉を書いたが、最近の私がしきりに気にしている言葉を援用すれば(これとて適切な説明を加えなければ同じく意味不明のままだが)、すなわち「末期の眼」に映じないものには関心が持てなくなっているのだ。なんのことはない、それはごく一般的な老化現象、もっと辛辣に言えば単なる耄碌だよ、という冷ややかな、いや同情あふれるご指摘が聞こえてきそうだ。悔しいけどそれに抗弁することはできない。なにしろ一分前に飲んだ薬さえ覚えておれなくなり、ご丁寧に日にちと回数を毎度記録する紙片を目の前に貼っている今日この頃だから。
いいかげん遁辞の上塗りはやめよう。ずばり聞く(誰に?)、これ以上続けるつもりか、それとも尻尾を巻いて退散するか。
続ける、作品を再度読み返さず、あれら意味不明の紙片を頼りに、なんとか『或る聖書』に挑戦してみる。
(整形外科の病棟は三階である。六畳ほどの広さの個室の窓から見上げると、いつも車で渡っていた跨線橋が見える。いま汽笛を鳴らして貨物電車が通過したようだ)
この作品が小川国夫の全作品の中でどの程度の位置を占めるものなのか。たとえばいま手元にある新潮社版作品集でも巻頭を飾っていることから分かるように、本作品が小川国夫の代表作であり、作者もそう自負していたと考えられる。ところが自らを小川国夫のよき読者ではないにしても、少なくともよき理解者と自負していた(つまりは思い込みなんだろう)私なのに、じっくり最後まで読んだのは今回が初めてであることをまずは白状しなければならない。
端から言い訳じみて恐縮だが、一つの文学作品を批評する切り口は多様かつ多層である。つまりすべての文献や資料をおさえて、たとえば卒論指導の教授にとやかく言わせないほどの緻密な、そして客観的な(危うく科学的な、と言いそうになった)批評というものがある。ところが他方には作者については何ほどのことも知らない、ましてやその作品が文学史上のどのような位置を占め、どのような新要素を加えたかなど一切頓着せず、ひたすら作品世界をただただ味到しての素朴な感想もある。どちらが優れておりどちらが劣っているとは言えないはずである。つまり作品の多様かつ多層の切り口…
(また窓を見上げる。雲は多いが珍しく青い部分もある。うろこ雲? 鰯雲? 一瞬なぜか初秋の空を思った。あゝそのころは妻の手術も無事終わって、また以前のように二人で歩いているだろうか。あと三十分で午後六時、医師との約束の時間、手術かそうでないか最終的な診断が下される。)
今さら言うことでもないが、『或る聖書』を自分から選んだわけではない。別の同人がやるはずだったが今回は納得いくものが書けそうにない、と編集長に断ってきたそうだ。一方に納得いくものが書けそうにない、と正直に言っている人がいるのだから、口説き落とされたにしても引き受けた以上、理屈としては納得いくものを書かなければならない。やたらハードルの高い課題が押し付けられたことになる。いやいや、ややこしく考えることはやめよう。自信のないままつい引き受けてしまったのは、元修道士のお前なら書けるだろう、いや書かなければならない、との無言の圧力を感じたからである。地中海もの(そんな分類はないのかも知れないが)や東海もの(これもそうは言わないか)ならいざ知らず、キリスト教や聖書とくれば君が書くしかないだろう…
(六時にナースステーションで担当医から、当初の予想通りこの数日間の検査の結果も手術の必要性を示している。つぶれている箇所は脊椎上部なので、背中側からの切開ではなく脇腹から治療箇所までメスを入れなければならず、所要時間は約五時間。その予想外の長さにびっくりしている私に、大学病院などではいろいろ制約があってさらにかかる、との説明。大学病院での制約とは何かを聞こうとしたが、やめた。この誠実で有能そうな脊椎・脊髄の専門医(指導医でもある)を信頼してすべてを託することは初めから決めていた。)
元修道士? この際だからはっきり言おう、現在の境地は元キリスト教徒でもある。つまりどこかの信徒名簿に名前が残っているかも知れないが、実質的にはもう何年も前からキリスト教徒ではない、ということ。なら新たな地平を求めての、ウナムーノ流にそれ独自の(sui generis)キリスト者たらんとしているのか?(いま唐突に小川教ということばが浮かんだ、結局この文章はその言葉にたどり着くまでの苦しい道筋ではないか、といま思っている)。いや、キリスト教に限らず、仏教、ユダヤ教、イスラム教などすべての既成宗教にも属していない。ならば無神論者か? それには少し間をおいて、そうではない、と答えざるを得ない。いや、問題は手前の信仰あるいは不信仰告白などではない、『或る聖書』についてである。
そのような次第であるなら、私は『或る聖書』を批評する適任者ではないだろう。しかし言い訳じみて(その通り!)申し訳ないが、作品批評の切り口は多様であり多層に亘る。この元キリスト教徒の位相からの発言もそれなりに意味があろう。簡単に言えば私の場合、端から護教論的立場から自由であるということだ。そうだ話をここから始めよう。
ひと昔前だったら、いやほんの最近まで(もしかしたら今も?)、といってそれは日本ではなくキリスト教圏の話ではあるが、小川国夫は異端者扱いをされていたであろう。なぜなら正真正銘の聖書に対抗して独自の「聖書」をでっちあげようなどとは神を恐れぬ不逞の輩以外の何者でもないからだ。そして小川国夫の全作品はあの悪名高き「禁書目録(Index librorum prohibitorum)」に登録されていたであろう。第二バチカン公会議後、つまり一九六六年以降、その拘束性が解除されたが、しかしその精神はいまだに生き続けているに違いない。最近カトリックの本を見たことがないので分からないが、ほんのひと昔前まで、カトリックの本(つまりカトリック関係の出版社から刊行される本)の奥付には Nihil obstat(教会の教えに抵触せず)とか Imprimi potest あるいは Imprimatur(印刷可なり)とのお墨付きが印刷されていた。どこからそんな判定が下されていたのだろう? ローマ教皇庁正邪検省の出先機関みたいのがあったのだろうか。
だから私には、キリスト教側から、つまり教会側から、少なくとも私の知る限り、この作品に対する厳しい批評もしくは抗議がいっさいなされなかったことをむしろ奇異に感じる。ここで思い起こされるのは、遠藤周作が『沈黙』(一九六六年)を発表した前後の、氏ご自身を含めてのある緊迫した状況である。そのころJ会神学院で遠藤氏を招いての講演会が企画され、私が氏の送り迎えの役を仰せつかったことがある。当時確か町田市にあった氏のご自宅についての記憶もあるが、それは別の時で、その時は成城大学(成蹊大学?)で講義後の氏をタクシーで神学院までお連れしたはずだ。さすがの狐狸庵氏(あるいは雲谷斎氏)もいささか緊張の面持ちであったことを覚えているが、講演の内容はきれいさっぱり記憶から消えている。しかし氏の心配も杞憂に終わった。おおむね教会側から好意的に迎えられたからである。
しかし今考えても、この『沈黙』には神学的な側面で教会にとっての危険思想はほとんど含まれていなかった。この意味で、遠藤周作という作家は氏の傾倒した先輩作家のモーリャックやグレアム・グリーンと並び称されてしかるべき模範的な「カトリック作家」であった。
だから氏にとって、神学の勉強すら始めていない一介の哲学生から思わぬ批判を浴びて意外に思うと同時に腹立たしかったのではなかろうか。事実氏から別の折に(それがいつのことだったか記憶にないが)「君は直接会ってる時はにこにこ愛想がいいが、書くものは厳しいね」と言われた。カトリック修道女が発行している「あけぼの」という雑誌に書いた私の『沈黙』論を指しての言葉である。
(ここで家に戻った際、遠藤周作についての三つの文章が収録されている私家本『島尾敏雄の周辺』を持ち帰る。すなわち「神の沈黙とは? ――遠藤周作氏の近作をめぐって」、「私にとってキリストとは何か 『死海のほとり』評」、「魂の真実を描く困難さ 『イエスの生涯』評」である。あとの二つは共に「朝日ジャーナル」掲載)。
三つの評論を読み返してみた。確かに痛いところをついた(別言すれば禁じ手を使った)批評ではあるが、書かれた方としては何とも憎たらしい文章だったと思う。たとえば沈黙論の核心部分は、こうなっている。「神の沈黙に対する作者の態度が、いささか性急にすぎたのではないか…神の沈黙をテーマとする本書が、いささか騒がしい音色をかなでるのは、ロドリゴの声と作者の声が奇妙に入り混じって聞こえてくるせいかもしれない」。そしてこう結んでいる。「泥沼が実は<黄金の国>であり、神の恩寵が豊かに流れる国であった、という逆転劇、つまり弱者の復権がなされるにはロドリゴはもう少し苦しまなくてはならない…その逆転劇はまだ始まっていない。もしそれが書かれるとしたら、実は『沈黙』が終わったところから新たに書き出さなければならないのではないか」。
『死海のほとり』評はさらに手厳しい。「…などは、いささか被害妄想的であり、作品の持つ革新性、現代性とは裏腹に意外と古くさいセンチメンタリズムが透けて見える。…つまり偽悪家めいた言葉が作者の肉声とおぼしき形で吐き出されるということは、それだけ作者が対象<たとえば作者にとっての正統的キリスト教の総体、あるいは光と影、偉大と卑小、罪と恥などというドラマを可能にする枠組みそのもの>に寄りかかっているからだと言えなくもないのである」。そして止めの一撃。「前作『沈黙』で、土壇場のロドリゴに神の声を聞かせたのは作者のそうした善意であるというのが私の率直な感想であったが、今回の作品でも、たとえば飢餓室に連れてゆかれるねずみ<コバルスキという元修道士>のかたわらに、同じく尿をたれながら歩いてゆくキリストの姿を二重写しにせざるをえなかったのも同じ善意からであると思われてならない。そしてこの場合、善意あるいは説明過剰はむしろ裏目に出て、作品の持つ迫真性、現実性を殺ぐ働きをしている。むしろ期待したいのは、思い切った省略法、あるいは度胸をすえた異端性であると言ったら、それこそ悪意に満ちた注文でろうか」。
かつての自分の文章なのに、引用していてドキドキしてくる。まさに禁じ手乱発である。遠藤氏はこんな若造の言うことなど歯牙にもかけなかったであろうが、もし私がこう言われたとしたら、やり場のない怒りを鎮めるのに優に数日はかかったであろう。
(それからまただいぶ時間が経って、いまは妻の手術が無事終わるのを同じ階の家族控室で待っているところ。午後一時半に始まって今五時十分。あと二時間だろうか)
小川国夫は聖書を携えて最後の入院生活に向かった、と伝えられている。氏がいかに生涯にわたって聖書を座右の書としたか、そこからつねに霊感を受け、そしてそれを発条として彼独自の言葉を紡ぎ出してきたか、の動かぬ証拠として、一種の美談として伝えられた。またプロテスタントとカトリックの共同訳聖書の日本語担当(?)の助言者として積極的に協力した。また持っているだけでまだ読んでないが(そんなことばかりで申し訳ない)八木誠一氏とキリスト教をめぐっての対談集も出している。
その彼が『或る聖書』を発表したのである。とうぜん彼なりの自負・自信があってのことであろう。しかし率直に言わせてもらおう。私が最終的に感じたのは、先の一枚のメモにあったものなのだ。「崖をよじ登っているのはよく伝わってくるのだが、果たしてそれに何の意味があるのか、ということ」。崖をよじ登る目的、つまり作品執筆の動機・目的はなにか。キリストの時代の資料・データを渉猟して、独自の「外伝」を書こうとしたのか。それともキリスト教の正統思想に対する異議申し立て、つまり自らの異端思想を展開しようとしたのか。
キリスト教会はまさにそれら異端者の群れの累々たる屍の上に立ってる。逆に言えばそれら異端と闘うことによって、つまりギリシア神話のアンタイオスが大地に触れるたびに力を得てきたように、教会は存続することができたのである。小川国夫は……
(先日、ほぼ六時間にも及ぶ大手術が無事終わった。今日は術後四日目。月一度、小高浮船文化会館での「島尾敏雄を読む会」の日である。もともと完全看護態勢の病院だし、さしあたって何も予定されていない午後の二時間、念のため息子に留守を頼んでいつもの通り車で出かけた。毎回七、八名の参加者が熱心に話を聞いてくれる会なので、結果的に私にとって大いなる気分転換になったし、また望外の幸いと言うべきか、話している途中、あっこれは今まさに書きあぐねていた小川国夫論の結論部分に充当できる、と小躍りしたいほどの確信を覚えた瞬間もあった。もちろん以下の文章すべてがその時に話したものではないが、大筋は変わっていない。そういった幸運な状況が生まれた要因の一つは、受講者の中に「隠れ小川教信者」が一人いたことである。つまりこちらが暗中模索の状態の中で出す不確かな発信音を確実にキャッチできるアンテナを意識したとき、自然と言葉が出てきたのである。)
さて小川国夫はそうした時代、つまり第二バチカン公会議( 一九六二年~一九六五年、教皇ヨハネ二十三世のもとで開かれ、後を継いだパウロ六世によって遂行された)後の寛容の時代、雪解けの時代に本格的な作家活動を始めました。フランス留学後に本格的な作家活動に入ったという点では遠藤周作と似ていますが、しかし公会議が二人に及ぼした影響という点では大いに違っています。つまり遠藤周作が『沈黙』を発表した一九六六年は、まさに第二バチカン公会議直後の大波がこの極東の日本にも押し寄せてきた年です。修道会の内部でも守旧派の神父たちと時代の閉塞状況を破りたい若い神父たちや神学生たちとの溝が私の目にも明らかになってきていました。そしてこれを書きながら改めて当時の自分のこともはっきり見えてきたような気がします。つまりその頃いろいろ煩悶のすえに修道院を去って行った人たち、そしてこの私自身、やはり無意識のうちにこの大きな波に激しく揉まれていたということです。自分から進んで修道院の門をくぐったのに変な話ですが、還俗への決断が単に個人の意思だけでなく、その背後に大きな時代変化の波があったことを、今日になってはっきり感じるのです。いやいや今は自分のことではなく、遠藤周作や小川国夫の話に戻しましょう。
文明批評家的才能に恵まれていた遠藤周作は時代の流れにきわめて敏感に反応しましたが、しかし小川国夫がそうした時代の流れに乗ったのか、と言えば決してそうではありません。彼が雑誌「展望」に『或る聖書』を発表したのは一九六九年、『沈黙』のわずか三年後のことですが、彼はそうした時代風潮に対しては超然としていました。つまり遠藤周作のように教会からどう思われているかなど、いっさい気にしていなかったと思います。先日、彼のそうした姿勢を考えていた時、唐突に<小川教>という言葉が浮かびました。彼はキリスト教というものに、実に独特な関わり方をしたと思うのです。つまり彼の<生きる>にとって有用であるかぎりのものを受け入れますが、それ以外のことにほとんど関心を示さなかったのではないか。生きることこそ彼にとって焦眉の課題であり、常に試みの笞であり続けました。病弱の故でしょうか、それとも生来の禁欲的志向の故でしょうか。私が彼と初めて出合ったころに出た短編集の題名『生のさ中に』はその意味でも象徴的だと思います。
彼が生涯惹かれ続けた聖書とは、彼にとって何だったのでしょうか。文字通りの教典だったのでしょうか。もちろんそうでしょう。しかし聖書は彼にとってもう一つの意味を持ち続けました。言葉の採石場です。ユダヤ民族を一言でいえば契約の民、つまり神と言葉で結ばれていることを強く意識した民族です。その民族によって書かれ守られてきた聖書は、まさに言葉が生まれる創生の場所、輝くような新しいことば・表現の採石場であるのは当然です。小川国夫はこの聖書に生涯魅了され続けました。しかし彼が長年の聖書熟読の成果として、彼独自の「新約聖書」を書こうとした、などと考えるのは早とちりです。遠藤周作が『沈黙』執筆にかけた覚悟のようなものは小川国夫には無かったでしょう。ではそうした世間の「早とちり」を小川国夫はどう受け取ったでしょう。彼はそうした世間の評価を否定も肯定もしません。それは世間の勝手であって、私自身とは関係ない、と思っていたのではないでしょうか。藤枝のお家の中庭にある、あの小さな庵に籠って毎夜言葉を紡ぎ、疲れたら深夜の蓮華寺池を彷徨した彼にとって、実は教会も…(ちょっと間が入る)…そうです、『或る聖書』は小川国夫の書いた新しいタイプの霊的指南書、つまりロヨラのイグナチオの『霊操(Exertitio Spiritual)』のようなもの、《生きる》という究極の課題に向かって、己が精神をどう鍛えるか、どう導くか、の指南書なのであります。
(あゝそこまで言う? 言ってしまったものは取り返しがつかない。で言葉に詰まって、手元のメモを覗く。
※あらゆる夾雑物を排した、しゃりしゃりした原初の言葉、
※島尾敏雄が彼の文章を評した言葉「竹をかけかけたような…」
※「物と心」の少年のように、採石場から拾ってきた原石を研ぎ始める…)
ところで最近、遠藤周作が大学時代の同級生であった修道女に宛てた書簡が発見されたと新聞が報じました。へえそんなものが新聞記事になるんだ、と読んでいきますと、遠藤氏のこんな言葉が目に付きました。「…日本のなかで一見、神の在い(原文ママとあるがもちろん無いの意味)ようにみえるどんな小さなものも、神を必死で求めていることを浮びあがらせてみたいと考えています…」。たとえばかつての私なら同じような文章を書いたかも知れません。しかし小川国夫はけっして、けっしてこの手の文章は書かなかったでしょう。『沈黙』の作家と『或る聖書』の作家の決定的な違いがそこにあります。
小川国夫を一言で表現しようとしたら、私にはそれが「勁い人」ではないかと思われます。この字が表すのは「上下の枠のあいだに縦糸をぴんと張った姿」です。彼を思い出すとき、ごく小さなことですがいかにも彼らしいしぐさ(彼は仕種と表記しますが)が浮かび上がってきます。彼が最後までそうであったかどうかは知りませんが、彼は煙草を買うと実に奇妙な儀式を始めるのです。つまりセロハンを箱からきれいに抜いて、今度はそれに頭の部分を煙草一本分破いた箱を逆さまに入れていくのです。即席煙草ケースのでき上がりというわけでしょうか。だれでも変な癖を持っています。しかし彼の悠揚迫らぬしぐさは、私には癖というよりなにかそれ自体が意味のある儀礼のように思えました。つまり彼の間合いには独特なものがあり、いつの間にかこちらをもその悠長な流れに引き込んでしまう独特な魔力がありました。いやもっと言えば、彼のそうした独特な仕草は、私には彼が言葉を(そして言葉によって)彫琢するときのその工程そのものが、たまたま身体の所作として表出されたとさえ思えたのです。
小川暁夫さんは父国夫氏を構えのない人と評しました。何十年も身近に氏を見てきた人の言葉に逆らうのはそれこそ烏滸の沙汰でしょう。でもあえて言わせてもらえば、実の子をも錯覚させるほど、彼はその独特な構えを自然体にまで高めた、と言ったら言いすぎでしょうか。つまり彼は剣の使い手のように、生に立ち向かう独特な構えをいつのまにか編み出していたわけです。小川教に惹かれる人が跡を絶たないなどと言えば、なにかはた迷惑な宗教のように聞こえるかも知れませんが、けっしてそんなことではありません。信徒たちは先ず徒党を組みません。信徒はそれぞれ孤立しており、便宜的に集まることはあっても互いに交流することもなく、それぞれは己れが教祖と深く結ばれていることを確信してやみません。ご利益、そんなものを求めて門を叩いたのではありません。生という崖をよじ登ることにかけて彼以上の師は他にはいないからです。苦しい姿勢から次の手掛かりへとよじ登るその間合いと力の入れ具合を彼がまず実践して見せてくれたからです。もちろんそれは、言葉に向かっての、言葉による彼の日々の苦闘です。
文士という言葉は、たぶん現在は死語に近いでしょう。でも彼は自分を文士と呼んではばかるところがありませんでした。しかし小川教とか文士とか、いささか抹香臭い言葉を使いましたが、彼が自分を何かを教え諭す者と見做していたと考えればそれこそ誤解です。自分の不器用な生き方から学べるものがあれば学んでほしいと願っていたにすぎません。その意味で、彼と郷里を同じくする若者たちは実にいい先達を持っていることに気づかなければなりません。いやすでにじゅうぶん気づいているように思われます。生前、静岡新聞社が出版したDVD付きの『故郷を見よ 小川国夫文学の世界』という本があります。五〇ページほどのものですが写真や絵入りの大判の本です。それを見ると、小川国夫は生きている時から、すでに伝説を作り上げた人であることがよく分かります。先ほど言った構えのある人の真骨頂がたくまずして顕れ出ています。ちょうど能のシテのように、しかし鳴り物抜きで、人々や風景という書き割りの中の、もっとも自分にふさわしい位置を静かに占めています。
小川国夫は勁い人でした。と同時に、実に幸福な生を全うした人と言わなければなりません。遠藤周作はほんの駄洒落のつもりで雲谷斎を名乗ったと思いますが、私の方は介護に伴う実際のものとして日々その現実を生きてますので、なおさら小川国夫の幸福な生涯を、いささかの妬みを込めて羨ましく思うのであります。
さて以上でいささか、いや大いに尻切れトンボの気味がありますが、今日の、いつものように準備不足の拙いお話を終わります。